キャリアステップ紹介では、名古屋鉄道の総合職技術系社員の入社から現在まで
のキャリアや業務内容、成長の過程を詳しく紹介しています。総合職技術系社員の
活躍とキャリア形成を具体的にイメージできる内容となっています。
(2024年10月時点)

大規模プロジェクトを成功に導き、
地域の発展に全力を尽くすのが自分の使命。
アシスタントマネージャー
Hiromasa.I
鉄道事業本部 土木部 建設課
2016年入社 自然科学研究科 環境デザイン学専攻修了
STEP 1
入社1年目
(2016年)
鉄道現場(運転部門、施設部門)研修
入社1年目は鉄道現場研修として運転部門や、施設部門(土木、電気、車両)の業務を経験しました。鉄道が安全に、正確に運行している「当たり前」の裏には、多くの人が関わっていることを理解し、そのプロ意識の高さや、名古屋鉄道の使命を体感することができました。
STEP 2
入社2年目
(2017年)
土木保守現場の東部土木管理区に異動
入社2〜3年目には土木管理区へ配属され、線路や土木構造物の維持管理の基本となる定期検査や保修工事を担当しました。その際に台風やゲリラ豪雨といった災害対応を行い、無事に電車が走り何事もなくお客さまが電車をご利用されているのを見たときは、鉄道の安全運行を担うやりがいを感じたとともに、責任感がより強くなりました。
STEP 3
入社4年目
(2019年)
土木部建設課に異動
鉄道高架化や駅改良といった大規模プロジェクトに携わり、土木構造物の設計や施工、工事完成までの他部署との工程調整役を担いました。これにより、技術的な知識を深めることができただけでなく、多くの課題に対して自ら解決していく力が身につきました。加えて、担当するプロジェクトをスムーズに進めるために、関係部署を巻き込みゴールを目指すマネジメントスキルを養うこともできたと感じています。
STEP 4
入社6年目
(2021年)
土木部建設課 大規模プロジェクトのリーダー
鉄道高架化や駅改良プロジェクトについて、多くのステークホルダーと調整や交渉を行い、より主体的に推進していく役割を担いました。特に関係自治体の皆さまとは密に連携をとり、将来に渡って信頼し合えるWin-Winな関係を構築することが求められるため、より実践的なコミュニケーションスキルが向上しました。また、駅のみならず、その地域全体を見渡し、長期目線で考える俯瞰的な視点を持つことができました。
STEP 5
入社9年目
(2024年)
将来を見据えた鉄道施設の実現へ
鉄道高架化や駅改良プロジェクトを通じて、輸送サービスの質的向上を図り、今後も沿線地域の発展や駅を中心としたまちづくりに貢献するための具体的な施策を統括するリーダーに。長期的な目線を持ち社会の変化に目を配りながら、業務効率化を実現する鉄道施設への改良を推進するとともに持続可能な鉄道の安全運行に貢献していきます。
入社動機

私が名古屋鉄道を志望したきっかけは、通学に利用していた高校生の頃の出来事です。ある日、それまで地上を走っていた線路が高架化されて駅も新しくなり、電車から見える景色が一変しました。やがて駅周辺が賑わい、綺麗な街に生まれ変わっていく様子を肌で感じて「鉄道の駅が新しくなると街全体が変わる!」という影響力の大きさにとても惹かれたのです。また名古屋鉄道は地域を支える多種多様なサービスを展開しており、将来自分が幅広い分野に挑戦できると感じたことも魅力でした。
これまでのキャリアを振り返って

高架化事業や駅改良プロジェクトといったスケールの大きな仕事は、たくさんの人々と連携しながら進めていくものです。それらに携わる上では課題解決に向けた粘り強い交渉や困難に打ち当たる場面が多々ありましたが、それぞれの経験が私自身を成長させる大切な糧となりました。今は私の失敗を支えてくれた人々の存在に深く感謝するとともに、人と人との熱いつながりが大規模プロジェクトを成功に導くという真実が、私の日々の原動力となっています。
今後の夢・目標
将来的な人口減少への対応や持続可能な社会の実現が求められている中、解決策の一つとして駅を中心としたコンパクトなまちづくりが注目されています。私は沿線地域の人々と連携してこのまちづくりを推進しつつ、出発点となる名古屋鉄道の駅を、利用者の賑わいや愛着にあふれた素敵な思い出となる場所にしていくことを夢に描いています。その実現に向けて、鉄道の安全運行確保をベースに必要とされる名古屋鉄道の姿を追求し続け、地域を守り、造り、拡げていくことに力を注ぎたいと考えています。
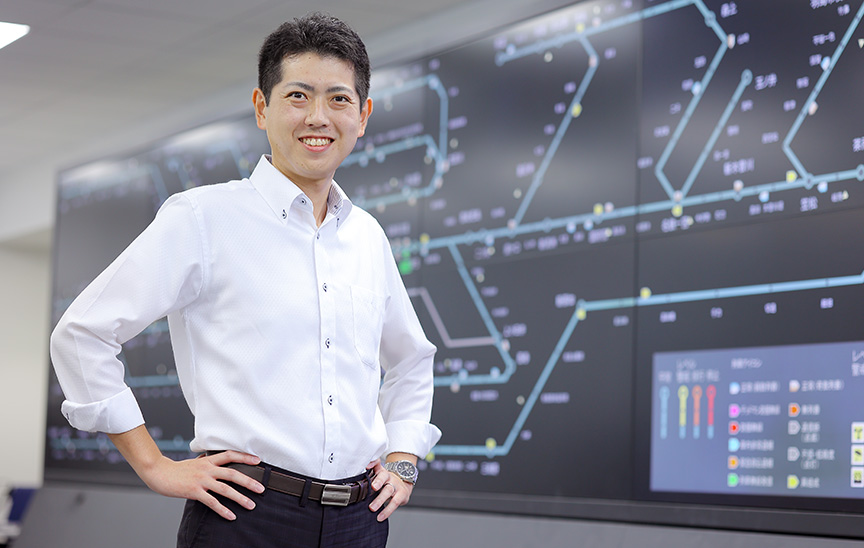
名鉄の高度な現場力をもとに、
より安全で快適な鉄道を目指して邁進。
アシスタントマネージャー
Kazuma.S
鉄道事業本部 運転保安部 運転指導課
2014年入社 自然科学研究科 機械科学専攻修了
STEP 1
入社1年目
(2014年入社)
鉄道現場(運転部門・施設部門)研修
運転部門の研修にて、乗務員として当社の根幹である鉄道事業の最前線の業務を経験しました。ドア操作や確認作業など、業務一つ一つがお客さまの安全・安心に直結しており、鉄道事業における安全の重要性について実務を通して学ぶことができました。また、乗務員として車両を「使う」という経験は、その後の車両部門への配属時に、自部門だけでなく、様々な立場から車両について考えるきっかけとして生かされました。
STEP 2
入社2年目
(2015年)
車両部 舞木検査場
検査業務に携わり、実際に自身の手で車両を整備することで、その構造や仕組みなど車両の基礎を学ぶことができました。業務を遂行する中で、たった1つの作業ミスであったとしても、大きな車両不具合につながる可能性があるという怖さを知るとともに、作業ミスを防ぐ仕組みづくりの重要性を実感しました。
STEP 3
入社5年目
(2018年)
車両部 舞木検査場 検査工程作成を担当
検査場事務所で定期検査の計画作成と管理業務を担当しました。机上で計画するだけなら簡単ですが、保有するデータや情報だけでは現場を常に正しく判断できるとは言えません。そのため、都度現場に赴き、「自分の目で確かめ」「自分の耳で声を聴き」「自分の肌で感じ」「自分で考える」ことを心掛けました。まさに、「現地・現物・現人」という三現主義を地で行く経験ができました。
STEP 4
入社7年目
(2020年)
車両部 車両課 車両検査業務の効率化プロジェクトを担当
車両検査業務の効率化に向けた検討を進めるなかで、ステークホルダーとの調整が必要な場面を経験しました。お互いの課題の本質はどこにあるのか、そして今まで見えていなかった解決の糸口はないのか、様々な観点から論理的に物事を捉え、整理する能力が養われたと思います。
STEP 5
入社9年目
(2022年)
運転保安部 乗務員用タブレット端末の導入・開発を担当
乗務員用タブレット端末に関する業務を担当し、予算管理、システム開発、現場の端末運用支援など、プロジェクト全体を統括しています。DX技術に関する知識・スキルだけでなく、列車運行管理、乗務員教育、労務管理など、様々な運転に関する業務を幅広く理解し、俯瞰的な視点からいかに全体最適解を見出すかが求められています。
入社動機

広く社会の役に立つ仕事がしたいと思っていた私は、誰もが当たり前と思っていることを当たり前に継続させる役割を果たすことが大切と考え、公共インフラ業界を志望しました。そんな就活の中で非常に印象的だったのが、当社の企業説明会で聞いた「名鉄グループは、お客さまの人生における様々なポイントで、様々なサービスを提供できる」という言葉です。機械工学系出身という自分の経歴を活かして毎日定刻通りに電車が走り続ける当たり前を支えたいと思うと同時に、将来的にいろいろな分野に挑戦できる可能性に大きな魅力を感じ、入社を決意しました。
これまでのキャリアを振り返って

入社からこれまでの10年を振り返ると、常に現場に支えられてきたと感じています。乗務区や検査場という第一線の現場で働く中で、技術に加えて列車運行を担う一員としての心構えや責任の大きさを学び、鉄道従業員として成長できました。数々の現場経験は今も私の礎となっていますし、前例のない取り組みに挑戦する機会もたくさんあったように感じています。例えばすべてが手探りで現場スタッフに対して厳しい指示を出さなければいけない場面もあり、時に辛辣な意見を返されることもありましたが、皆が一緒に考えて作業を進めてくれて乗り越えることができました。こうした現場力の強さは名古屋鉄道の大きな強みであり、これからもそれを維持できるよう現場サポートに全力を注ぎたいと考えています。
今後の夢・目標
近年、タブレット端末をはじめデジタル技術が驚くべきスピードで進化しています。それらをどうすれば運転業務と掛け合わせられるか考え、「名鉄といえば乗務員タブレット」と呼ばれるような、新しい運転業務のあり方を生み出していきたいと思っています。それによってすべての乗務員に「名鉄の乗務員になってよかった」と感じてもらうとともに、あらゆるお客さまにより安全・安心・快適に利用いただける鉄道環境の構築を目指していきたいと考えています。また、将来的には鉄道にとどまらず他の分野にも挑戦し、これまでの車両部門・運転部門の経験を活かした「鉄道×〇〇」というマッシュアップで新しい地域交通の支え方を発信していきたいと思っていま。

新たな技術を追究し、
鉄道業界の事故を減らす新システムの開発に挑戦中。
Kazuki.K
鉄道事業本部 電気部電気課
2018年入社 工学部 電気電子工学科卒
STEP 1
入社1年目
(2018年)
鉄道現場(運転部門)研修
駅係員として3カ月間、車掌として6カ月間の研修を行いました。鉄道の安全・安心・安定輸送を実現するため、現場の方々が日々高い安全意識と責任感を持って働いていることを知りました。名古屋鉄道の根幹である鉄道事業の最前線を経験し、社会的責任の大きさを痛感しました。
STEP 2
入社1~2年目
(2019年)
鉄道現場(施設部門)研修
土木1.5カ月、車両1.5カ月、電気2カ月の計5カ月の間、技術3部門の現場業務を経験しました。技術現場の仕事は駅係員や車掌と異なりお客さまと直接関わることはないですが、鉄道事業の縁の下の力持ちとして、電車が安全に走るために大変重要な役割を担っていることを実感しました。
STEP 3
入社2年目
(2019年)
中部電気管理区
電気管理区へ配属され、架線や変電所、信号機、表示器等の鉄道電気設備の保守業務に従事しました。鉄道に関わる電気設備の幅広さ、保守業務の重要性を体感し、「絶対に輸送障害を発生させない」という電気現場の方々のプロ意識の高さを肌で感じることができました。
STEP 4
入社4年目
(2021年)
名鉄EIエンジニア※へ出向
名鉄EIエンジニアへ出向となり、無人駅への対面インターホンの導入を含めた無人駅管理システム、ホームから転落されたお客さまを検知し運転士へ通知する新たなシステムの構築など、鉄道業界で当社が初となるシステムの検討、開発、導入を進めました。新たなシステム開発の難しさを痛感するとともに、各設備の知識や、メーカーとの交渉力、どんな状況下でも打開策を見つけ出し最後までやり遂げる力を身につけることができました。
※名古屋鉄道の電気部門が独立して誕生したグループ会社。名鉄電車を安全に運行させるために必要な電気設備の設計や工事等を担う。当社からの出向者も 多く、一体となりプロジェクト推進を行うことも多い。
STEP 5
入社7年目
(2024年)
電気部 電気課
現在は電気課へ異動し、高架工事等の工事案件の管理や新システムの導入および検討を進めています。また、他の鉄道会社との窓口も担っており、他社の知識や技術を学ぶのも私の業務です。これにより、複数の工事案件を管理・推進する力や、他部署や名鉄EIエンジニアを含めた他社との調整力が身についていると思います。また、新規案件を社内で立案し説明する論理的思考力が日々鍛えられていることを実感します。
入社動機

学生時代に学んだ「電気」に関わりながら社会に貢献できる仕事がしたいと思った私は、人々の日々の生活を支えるインフラ業界を中心に就職活動を行っていました。そして鉄道会社には、変電所など高電圧のものから信号機や表示器など低電圧のものまで多種多様な電気設備があることを知り、それらを勉強することで幅広い知識が身につくことに大変興味をそそられました。また、人々の生活に対する鉄道事業の高い貢献度も大いに魅力に感じ、中部圏に広く事業を展開する当社であれば電気技術を通じて確実に社会に貢献できると考え、入社を決めました。
これまでのキャリアを振り返って

これまでのキャリアを振り返ると、新技術の活用や業務効率化など電気部として求められる課題に常に関わることで自分自身が成長できたように感じています。特に名鉄EIエンジニアに異動した際は「どうすればお客さまに安心して鉄道をご利用いただけるか」という視点で新システムの検討や開発を行い、新しいシステムを作る中で知識や人脈、プレゼンテーション能力など多くの財産を得ることができたと思います。また、業務においてはチームプレイが必要不可欠で、チームの中で自分がどう動くか、求められている役割を考えながら物事を進める重要性も学びました。現在、名古屋鉄道のいくつかの無人駅で私が開発に携わったその新システムをお客さまにご利用いただいており、それによって自分が社会に貢献している実感と誇りを持って日々仕事ができています。
今後の夢・目標
ひとたび駅で人身事故が発生すると電車の運行が大幅に乱れ、お客さまに多大な迷惑をかけてしまいます。そこで私は現在、AI等を活用して人身事故を減らすことができないかどうかの検討を進めており、それを可能にする新たなシステム開発に挑戦しています。この取り組みは、お客さまに安心して鉄道をご利用いただくために、名古屋鉄道だけでなく鉄道業界全体として意義あるものになるはずです。将来的には最初に名古屋鉄道で導入し、その後鉄道他社にも活用してもらって、日本全体として誰もが安全、安心に利用できる鉄道社会を作っていきたいと考えています。このような取り組みを積極的に推進し、一層幅広く社会へ貢献していくことが私の目標です。
